
「営業支援」に関する裁判例(30)平成28年10月25日 東京地裁 平26(ワ)27467号 委託業務報酬請求事件(本訴)、(反訴)
「営業支援」に関する裁判例(30)平成28年10月25日 東京地裁 平26(ワ)27467号 委託業務報酬請求事件(本訴)、(反訴)
裁判年月日 平成28年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)27467号・平27(ワ)4159号
事件名 委託業務報酬請求事件(本訴)、(反訴)
裁判結果 請求棄却(本訴)、一部認容(反訴) 文献番号 2016WLJPCA10258015
要旨
◆通信機器等に係る販売委託契約の受託者である原告が、委託者である被告に対し、同契約書上、原告の報酬は販売契約額から物品代金、工事代金等を控除した額を元に算定するが、被告が物品代金を被告の仕入代金でなく同代金に一定額を上乗せした金額としたため原告に支払われるべき報酬の一部が支払われていないなどと主張して、報酬支払請求権に基づき、一部未払報酬分及び遂行した一部の受託業務の全部未払報酬等の支払を求めた(本訴)ところ、被告が、原告に対し、原告が販売契約額に工事代金等を含めたため原告に支払われるべき額よりも高額な報酬が支払われていたと主張して、不当利得の返還を求めるとともに、原告の債務不履行によって被告は再納品等の費用を要したと主張して、損害賠償を求めた(反訴)事案において、物品代金及び販売契約額の定めの意義を認定し、原告主張の一部未払報酬及び被告主張の不当利得をいずれも否定した上で、一部受託業務に係る全部未払報酬請求権と損害賠償請求権との相殺を認めて、本訴に係る請求をいずれも棄却し、反訴に係る請求を一部認容した事例
参照条文
民法415条
民法505条1項
民法648条
民法703条
裁判年月日 平成28年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)27467号・平27(ワ)4159号
事件名 委託業務報酬請求事件(本訴)、(反訴)
裁判結果 請求棄却(本訴)、一部認容(反訴) 文献番号 2016WLJPCA10258015
本訴平成26年(ワ)第27467号委託業務報酬請求事件,
反訴平成27年(ワ)第4159号
東京都中央区〈以下省略〉
原告(反訴被告) セキュアリンクス株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 三木昌樹
同 荒木美智子
東京都目黒区〈以下省略〉
被告(反訴原告) 関東通信工業株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 齋藤大
主文
1 原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
2 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,49万5215円及びこれに対する平成26年8月9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告(反訴原告)のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,本訴及び反訴共にこれを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余は被告(反訴原告)の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴に係る請求
(1) 被告(反訴原告。以下単に「被告」という。)は,原告(反訴被告。以下単に「原告」という。)に対し,1376万1416円及びうち1197万6202円に対する平成26年10月18日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(2) 被告は,原告に対し,5万7076円及びこれに対する平成26年7月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(3) 被告は,原告に対し,8262円及びこれに対する平成26年8月11日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 反訴に係る請求
(1) 原告は,被告に対し,3122万4796円及びこれに対する平成27年2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(2) 原告は,被告に対し,56万0522円及びこれに対する平成26年8月9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
原告と被告は,被告を委託者とし,原告を受託者として,通信機器等に係る販売委託契約を締結し,継続した取引関係にあったところ,当該販売委託契約においては,その契約書上,受託者である原告の報酬の算定方法について,「物品代金」,「工事代金」及び「リース残債」を合算した額を顧客に対する「販売契約額」から控除した額である「販売粗利益」を基礎とし,その80%又は90%とする旨が定められていた。
本件のうち,本訴に係る部分は,原告が,上記の「物品代金」について被告の仕入代金と解すべきところを被告が当該仕入代金に一定額を上乗せした金額としたために,原告に支払われるべき報酬の一部が支払われていないと主張して,報酬支払請求権に基づき,当該一部未払報酬分及びその遅延損害金の支払を被告に求める(上記第1の1(1)の請求)とともに,遂行した一部の受託業務についてはその報酬の全部が支払われていないと主張して,報酬支払請求権に基づき,当該全部未払報酬分及びその遅延損害金の支払を被告に求めた(上記第1の1(2)及び(3)の各請求)事案である。
また,本件のうち,反訴に係る部分は,被告が,上記の「販売契約額」について実際の施工に要する上記の「工事代金」に原告が一定額を上乗せした工事代金額を含めた金額としたために,原告に支払われるべき額よりも高額な報酬が支払われていたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,当該支払われるべき額との差額分及び当該差額分に対する反訴状の送達の日の翌日以降に生ずる年5%の割合による金員の支払を原告に求める(上記第1の2(1)の請求)とともに,原告が顧客から注文を受けた商品とは異なる商品の納品を被告に通知したことにより,再納品等のための費用を要したと主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権に基づき,当該費用相当額及びその遅延損害金の支払を原告に求めた(上記第1の2(2)の請求)事案である。
2 前提事実(括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認めることができる事実等)
(1) 原告は,通信機器の販売及び保守メンテナンス業務等を行うことを目的とする平成20年11月に成立した株式会社であり,A(以下単に「A」という。)がその代表者取締役を務めている。
被告は,電気通信機器の製造及び販売,保守並びに電気通信設備工事等を行うことを目的とする株式会社である。被告は,東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)の一次代理店であり,かつ,サクサビジネスシステム株式会社(以下単に「サクサビジネスシステム」という。)の一次代理店である日本フィールドワン株式会社の二次代理店として,NTT東日本及びサクサビジネスシステムの通信機器等の販売委託を取り扱っており,また,当該販売委託の対象となった通信機器等に係る工事については,株式会社ウィズネット(以下単に「ウィズネット」という。)に対し,平成19年2月1日付け「情報通信設備に関する業務委託基本契約書」に基づき,その設置工事等を委託していた。
(甲1,2及び乙517並びに弁論の全趣旨)
(2) 被告とAは,平成20年2月29日付けで,次の内容の「「NTT通信機器及びNTTネットワーク商品」販売委託契約書」(なお,各条項中の「甲」は被告を,「乙」はAをそれぞれ意味する。)を作成し,当該内容のとおり合意した(以下この合意による被告及びAの間の契約を「本件従前契約」という。)。(甲19)
「第1条 業務委託内容
(1) 契約期間
(略)
(2) 委託内容
ア、NTT通信機器及びNTTネットワーク商品の販売に関すること
イ、NTT通信機器販売において、リース等契約以外の場合(随時払い等)売掛債権の回収業務に関すること
ウ、NTT通信機器及びNTTネットワーク商品の販売における各種情報の提供に関すること。
上記実施にあたっての具体的内容は、業務委託仕様書による。
(3) 契約金額
ア、NTT通信機器(NTT商品外の現場調達品を要する場合は、それも含む)については、
① 販売額(工事料除く):1万円以上~100万円未満の場合販売粗利益の60%を支払う。
② 販売額(工事料除く):100万円以上~200万円未満の場合販売粗利益の70%を支払う。
③ 販売額(工事料除く):200万円以上の場合販売粗利益の80%を支払う。
NTT商品外のいわゆる現場調達品については、その都度、甲が物品単価表と同様乙にその内容を通知する。
イ、NTTネットワーク商品については、NTT支払手数料の80%を支払う。
具体的には、別途、交付する内訳表による。
(4) 契約金額の支払
(略)
第2条から第8条まで (略)
「付則」
[NTT通信機器販売粗利益の計算方法]
●販売粗利益=お客様との販売契約額-(物品代金+工事代金+リース残債)
●提供資料:物品単価表、リース料率表、商品カタログ等」
(3) 原告と被告は,本件従前契約におけるAの受託者の地位を成立後の被告〔編注:原文ママ「原告」と思われる〕に引き継がせることとし,平成20年12月26日付けで,次の内容の「「NTT通信機器及びNTTネットワーク商品」販売委託契約書」(以下「本件契約書」という。)及び「業務委託仕様書」(以下「本件仕様書」という。)(なお,本件契約書及び本件仕様書中の各条項中の「甲」は被告を,「乙」は原告をそれぞれ意味する。)を作成し,当該内容のとおり合意した(以下この合意による原告及び被告の間の契約を「本件契約」という。)。(甲3及び弁論の全趣旨)
ア 本件契約書の内容
「第1条 業務委託内容
(1) 契約期間
(略)
(2) 委託内容
ア、NTT通信機器及びNTTネットワーク商品の販売に関すること
イ、NTT通信機器販売において、リース等契約以外の場合(随時払い等)売掛債権の回収業務に関すること
ウ、NTT通信機器及びNTTネットワーク商品の販売における各種情報の提供に関すること。
上記実施にあたっての具体的内容は、業務委託仕様書による。
(3) 契約金額
ア、NTT通信機器(NTT商品外の現場調達品を要する場合は、それも含む)については、販売額(工事料除く):販売粗利益の80%を支払う。
NTT商品外のいわゆる現場調達品については、その都度、甲が物品単価表と同様乙にその内容を通知する。
イ、NTTネットワーク商品については、NTT支払手数料の80%を支払う。
具体的には、別途、交付する内訳表による。
(4) 契約金額の支払
(略)
第2条から第8条まで (略)
「付則」
[NTT通信機器販売粗利益の計算方法]
●販売粗利益=お客様との販売契約額-(物品代金+工事代金+リース残債)
●提供資料:物品単価表、リース料率表、商品カタログ等」
イ 本件仕様書の内容
「1.業務内容
(1) NTT通信機器及びNTTネットワーク商品の販売に関すること
(2) NTT通信機器販売において、リース等契約以外の場合(随時払い等)売掛債権の回収業務に関すること
(3) NTT通信機器及びNTTネットワーク商品の販売における各種情報の提供に関すること。
*別紙業務フロー (略)
2.対象地域
(略)
3.準備品等
(1) 甲で用意するもの
・名刺、受託者票、商品カタログ類、リース契約書等の各種書類、通信機器単価表、その他
(2) 乙で用意するもの
・営業活動に関する交通費等、その他
4.活動項目
(1) 販売業務及び目標
・自社情報に基づく、NTT通信機器及びNTTネットワーク商品の販売勧奨
・上記活動を通して、販売目標(販売額)は、年間、NTT通信機器(現調達品含む)は6,000万円、Bフレッツ等は30回線を目標とする。
(2) 契約業務
・受注に基づく、事前確認及び確認後のリース契約書の締結に関すること
(3) 報告・管理業務
・甲の定める注文書に基づき、注文内容、工事日等の詳細について、報告する。
(4) 営業担当者へのマネジメント業務
・トラブル対応等
(5) 甲が実施する共通業務
・電話受付
・電話受付等からの有効情報の乙への取次
・その他の営業支援業務
(6) 作業者及び人員数の届出
・甲の定める報告様式に基づき、乙は、営業活動実施日の1日までに甲に報告する。
・報告した内容に変更が生じた場合は、乙は速やかに甲に変更内容を報告する。
(7) クレーム等お客様対応
・訪問営業活動の実施に起因するクレームについては、原則「乙」にて対応するが料金、制度等に関するものは、委託の責任者である「甲」にて対応する。
・また、一次対応にて、お客様訪問が生じた場合は、「乙」にて対応する。
(8) 本仕様書に記載されていない事項は甲乙協議のうえ決定するものとする。」
(4) 原告と被告は,平成21年8月31日付けで,本件契約書第1条(3)ア及びイに定める割合をそれぞれ90%と定める内容の「「NTT通信機器及びNTTネットワーク商品」販売委託契約書」(以下「本件変更契約書」という。)を作成し,本件契約に関し,同年9月1日以降に工事が完了した業務については,当該第1条(3)ア及びイに定める販売粗利益又はNTT支払手数料の90%を被告が原告に支払う旨に変更することを合意した。(甲4及び13)
(5) 原告は,別紙1及び別紙2の各「顧客名」欄記載のとおりの各顧客に対して営業活動を行い,同各「売上日」欄記載の日にちに各顧客との間の通信機器等に係る契約を締結して,本件契約に基づく受託業務を遂行した。(甲22の2から22の19まで,26の2の2及び乙6の1から495の4まで並びに弁論の全趣旨)
(6) 被告は,原告に対し,別紙1の「弊社報酬(消費税抜)」欄記載のとおり,本件契約に基づく各報酬を支払った。(弁論の全趣旨)
(7) 被告の代理人弁護士は,原告の代理人弁護士らに対し,次の内容の平成26年8月6日付けの「回答書」と題する書面を送付して56万0552円の支払を催告し,当該書面が遅くとも同月8日までに原告の代理人弁護士らに到達した。(乙5及び弁論の全趣旨)
「1から4まで (略)
5 請求明細書2件の支払請求
(1) aクリニックの件
回答人は,aクリニック様に対し,被回答人が上記のように故意に成約した商品と異なる商品を納品・工事していたことが発覚したことを受け,改めて本来成約したL型商品を納品,工事せざるを得なくなりました。
これに要した56万0552円を速やかに添付の請求明細書にて指定された口座に振り込むよう請求します。」
(8) 被告の反訴に係る反訴状は,平成27年2月20日に原告に送達された。(当裁判所に顕著な事実)
(9) 被告は,平成28年6月23日に実施された本件第12回弁論準備手続期日において,原告に対し,後記3(4)アのとおり主張する損害賠償請求権を自働債権とし,後記3(2)アのとおり原告が主張する報酬請求権を受働債権として,対当額において相殺する旨の意思表示(以下「本件相殺の意思表示」という。)をした。(当裁判所に顕著な事実)
3 争点及び当該争点に関する当事者の主張
本件における主な争点のうち本訴に係るものは,①本件契約に基づく原告の報酬を算定する際の対象となる「販売粗利益」の控除項目である「物品代金」の定め(上記2(3)アの前提事実において認定した本件契約書第1条(3)ア及び付則。以下「本件「物品代金」の定め」という。)が被告の実際の仕入価格又は被告が定める金額のいずれを定めたものと解すべきか(本件「物品代金」の定めの意義)並びに②原告のした2件の受託業務についての報酬の未払が被告にあるかどうか及びあるとした場合の額いかんであり,反訴に係るものは,③当該「販売粗利益」の基礎項目である「販売契約額」の定め(上記2(3)アの前提事実において認定した本件契約書第1条(3)ア及び付則。以下「本件「販売契約額」の定め」という。)がその控除項目である「工事代金」以外に原告が定める工事代金額を含めることができるものとして定められたものと解すべきかどうか(本件「販売契約額」の定めの意義)及び④aクリニックへの納品不備による債務不履行に基づく被告の原告に対する損害賠償請求権の有無であり,これらの争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。
(1) 争点①(本件「物品代金」の定めの意義)に関する当事者の主張
ア 原告の主張
本件「物品代金」の定めは,被告の粗利益を計算するために差し引くべき販売物品に係る被告の実際の仕入価格を定めたものである。しかし,被告は,本件契約に基づく原告の報酬を算定する際に,この「物品代金」について実際の被告の仕入価格ではなく,これに1割を加算した金額を用いていた。この実際の被告の仕入価格を基にして当該報酬を算定し直すと,被告が支払った報酬との差額は,別紙1の「未払報酬(消費税込)」欄記載のとおりとなり,合計1197万6202円となる(なお,各支払日から平成26年10月17日までの年6%の割合による確定遅延損害金は,合計178万5214円となる。)。
被告は,本件「物品代金」の定めが実際の被告の仕入価格ではなく,被告の定めた物品代金額,具体的には,被告が原告に交付した物品単価表に定める金額であると主張しているが,一般に,会計処理上も,粗利益は,売上げから売上原価を控除したものと定義されている上,本件契約書において示された計算式も,明らかに同様の理解を示すものとなっているし,被告自身も,本件契約に基づいて原告の報酬を算定する際には,その計算書上,物品価格を「仕入価格」と表示している。
イ 被告の主張
上記アの原告の主張は,否認する。
本件「物品代金」の定めは,被告が実際に仕入れた際の価格を基にして,被告においてあらかじめ金額を設定するものである。本件契約書には,本件「物品代金」の定めの意義について,これを実際の被告の仕入価格と同額とする旨の条項はないし,通信機器メーカーからの実際の被告の仕入価格を示す資料を提供すべき義務も,定められていない。被告は,あらかじめ自由に単価を定めた上で,物品単価表又は通信機器単価表を原告に提供し,これに基づき原告が業務を受託するかどうかを選択するのである。そもそも,原告には,通信機器等を仕入れる権利がないのであって,被告が仕入額に自らの利潤を上乗せして単価表を作成することは,合理的な経済観念に沿うものである。
(2) 争点②(原告のした2件の受託業務についての報酬の未払が被告にあるかどうか及びあるとした場合の額いかん)に関する当事者の主張
ア 原告の主張
原告は,別紙2に記載のとおり,本件契約に基づく2件の受託業務を遂行した。当該受託業務に関する報酬は,平成26年6月30日支払予定分が5万7076円で,同年8月10日支払予定分が8262円となる。
イ 被告の主張
上記アの原告の主張のうち,被告が原告に対して平成26年6月30日支払予定分の報酬として4万3848円の,同年8月10日支払予定分の報酬として7650円の各支払義務を負っていたことは認め,これを超える額の支払義務を負っていたことは否認し,又は争う。
(3) 争点③(本件「販売契約額」の定めの意義)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
本件「販売契約額」の定めは,委託業務の原告による遂行によって被告が顧客又はリース会社から支払を受けることになる金額を指しており,その控除項目である「工事代金」以外に原告が定める工事代金額を含めることは,予定されていない。このことは,本件契約書第1条(3)アにおいて「販売額(工事料除く)」と定められていることからも,明らかである。しかし,原告は,顧客に対して実際の工事代金以上の工事代金が生じているとして,自らが定める工事代金額を加算した金額で顧客と契約し,この差額を含めた金額を「販売契約額」として被告に報告し,報酬を得ていた。
原告は,このように不正に加算した工事代金によって不当に利得を得ていて,これは被告の損失となるものであり,その金額は,別紙1の「過払額」欄に記載のとおり,合計3122万4796円に及んでいる。
イ 原告の主張
上記アの被告の主張は,否認し,又は争う。
本件「販売契約額」の定めは,その控除項目である「工事代金」以外に原告が定める工事代金額を含めることができるものとして定められていたものである。本件契約においては,原告は,顧客に対して商品を販売した後にも,工事の発注連絡や作業日程の調整等を行い,アフターサービスの一次的窓口として対応していることからすると,原告が工事代金として一定の利益を得ることを禁ずる理由はないし,工事価格の上乗せや価格の設定についての具体的な被告からの指示や被告との合意もされていない。原告は,被告に対し,本件契約に基づく顧客との契約を締結する前に,契約価格の内訳書及びリース契約確認書を送付して被告の確認を受けており,被告においてこのような工事代金の加算について認識していなかったはずはない。
(4) 争点④(aクリニックへの納品不備による債務不履行に基づく被告の原告に対する損害賠償請求権の有無)に関する当事者の主張
ア 被告の主張
原告は,本件契約に基づき,情報通信機器であるNX主装置のL型商品(税抜価格261万3600円)を顧客であるaクリニックから受注したにもかかわらず,被告に対し,L型商品よりも容量が小さく,単価が安いM型商品として受注し,その価格が262万5600円である旨を報告したため,被告は,原告の当該報告に基づき,M型商品を発注し,工事業者に設置工事を発注した上,原告にその報酬を支払った。このように,被告は,原告の誤った報告により,aクリニックに対する再納品及び再工事を強いられ,その費用として56万0552円の支払を余儀なくされた。被告は,原告に対し,平成26年8月8日,この債務不履行を理由として,56万0552円の損害賠償をするように催告をした。
イ 原告の主張
上記アの被告の主張は,否認し,又は争う。
第3 争点に対する判断
1 争点①(本件「物品代金」の定めの意義)及び争点③(本件「販売契約額」の定めの意義)について,併せて判断する。
(1) 上記第2の2(3)の前提事実において認定したとおり,原告と被告は,本件契約において,被告が原告に支払うべき原告の報酬につき,「販売額(工事料除く):販売粗利益の80%を支払う。」とし,この「販売粗利益」を「販売粗利益=お客様との販売契約額-(物品代金+工事代金+リース残債)」と合意していた(本件契約書第1条(3)ア及び付則)ものであるところ,上記第2の3(1)及び(3)のとおり,このうち本件「物品代金」の定め及び本件「販売契約額」の定めの意義について,当事者間に争いがある。
(2) まず,このうち本件「物品代金」の定めの意義(争点①)について検討すると,確かに,原告の主張するように,上記の「販売粗利益」の文言が被告の本件契約を含めた一連の取引から被告が得るべき粗利益を意味するものとすれば,本件「物品代金」の定めは,被告自身の当該取引における売上原価に属すべき被告の仕入価格を意味するものと解すべきとも考えられるし,また,被告が原告に対して「仕入価格」と表示した「支払手数料計算書」を提示していたり,Aからの「仕入れ値」の問合せに関する電子メールに対して被告の担当者が「仕入価格」を回答する電子メールを複数回送信するなど(甲5,6,10の1から10の3まで及び14),原告と被告が本件「物品代金」の定めについて「仕入価格」との呼称を用いていたことは,否定することができないところである。
しかしながら,本件契約書及び本件仕様書(甲3)や本件変更契約書(甲4),更に本件契約の元となった本件従前契約に係る契約書(甲19)(以下これらを「本件契約書等」と総称する。)には,本件「物品代金」の定めないしこれに相当する定めの意義について明示するところが全くないし,本件全証拠を精査しても,他にこれを認めるに足りる証拠もない。むしろ,上記第2の2(2)及び(3)の前提事実において認定したとおり,本件契約書等においては,被告から原告ないしAに対してNTT商品については「物品単価表」を,それ以外のいわゆる現場調達品についてはその都度当該物品単価表と同様の内容のものを通知する旨が明示されているのであり,証拠(甲5,6,11の1から12まで,乙497及び524の1から526の2まで)及び弁論の全趣旨によれば,被告が原告に対して通信機器等ごとに「参考小売価格」及び「お取引価格」が記載された「取扱商品取引価格表」,「〈定価〉」及び「〈仕切価格〉」が記載された「〈PLATIA〉商品価格表」並びに「参考小売価格(税抜)」及び「取引価格(税抜)」が記載された「Netcommunity SYSTEM αNX(typeS/typeM)取引価格一覧」及び「Netcommunity SYSTEM αNX(typeL)取引価格一覧」を交付していて,原告及び被告は,共にこれらの価格表に基づいた金額を「仕入価格」として原告の報酬を算定していたものと認めることができる。このことに加え,本件契約がNTT東日本の一次代理店及びサクサビジネスシステムの二次代理店として被告が調達する通信機器等を対象とする販売委託契約であり,被告のこれらの地位を不可欠の要素とするものであるにもかかわらず,本件契約において「販売粗利益」を算定する際の基となる「販売契約額」を顧客との交渉において定める際の原告の判断に羈束性があるものとうかがうことができず,かつ,本件契約における原告と被告の報酬割合がそれぞれ80%と20%又は90%と10%とされていて,原告の報酬割合が極めて高いこと(上記第2の2(1),(3)及び(4)の前提事実)をも併せて考えると,原告と被告は,本件契約において,被告が原告に交付する上記の価格表に記載された価格が実際の被告の仕入価格を基に被告が定めたものであったとしても,当該価格表に記載された価格をもって「物品代金」として報酬を算定する旨の合意をしていたものというべきである。
したがって,本件「物品代金」の定めが実際の被告の仕入価格を定めたものである旨の原告の主張を採用することは,困難であるというほかない。
(3) 次に,本件「販売契約額」の定めの意義(争点③)について検討すると,確かに,上記第2の2(3)の前提事実において認定したとおり,本件契約においては,原告の受託業務が被告に代わって通信機器等に係る設置工事込みの販売交渉,契約締結を行い,及び売掛金回収,各種情報の提供,トラブル対応等を行うこととされており,原告において通信機器等の設置工事等を行うことまでは予定しておらず,上記第2の2(1)の前提事実において認定したとおり,現に,通信機器の設置工事自体は,被告がウィズネットに別に委託していたものと認めることができる。これらの事実によれば,本件「販売契約額」の定めにウィズネットに支払うべき実際の工事代金額を超えて原告が定める工事代金額を含めることができるとする実質的な根拠に乏しいものとも,考えることができる。
しかしながら,そもそも,本件契約において「販売粗利益」を算定する際の基となる「販売契約額」は,「物品代金+工事代金+リース残債」を上回る金額が予定されているところ,上記(2)においても説示したとおり,この「販売契約額」を幾らとするかについての原告の判断に羈束性があったものとはうかがうことができず,この予定されているところを満たす限りにおいて,原告による顧客との交渉に委ねられていたものと解される。そして,当該「販売契約額」とされた額の中に実際の工事代金額を超える額の工事代金名目の額が計上されていたとしても,結局は,その差額についても,本件契約によって合意された割合に従って原告及び被告の利益に帰するものであることをも併せて考えると,原告による工事代金額の加算が原告と被告との本件契約の条項に関する明示又は黙示の意思ないし合意に反したものであるとか,ましてや被告の損失において原告が利益を受けた不当利得に当たると解することは,困難である(現に,例えば,証拠(甲26の1から26の3まで,乙88の1から88の4まで,479の1から479の4まで及び495の1から495の4まで)及び弁論の全趣旨によれば,原告が株式会社ジェイアール東日本物流,有限会社広栄運輸機工及び株式会社東京プロカラーラボに対してした委託販売について被告に送付した「御見積書」と題する各書面にはウィズネットに支払う工事代金よりも高額な取付設定工事費等が加算されて販売契約額が定められていたにもかかわらず,被告は,これについて特段の異議を述べることなく,単価表に基づいた物品代金及びウィズネットに対して支払う工事代金のみを控除した金額を販売粗利益として支払手数料計算表を作成し,原告に対して報酬を支払っていたものと認めることができる。)。
したがって,本件「販売契約額」の定めがその控除項目である「工事代金」以外に原告が定める工事代金名目の額を含めることができないものとして定められていた旨の被告の主張を採用することはできない。
2 続いて,争点②(原告のした2件の受託業務についての報酬の未払が被告にあるかどうか及びあるとした場合の額いかん)について,判断する。
(1) 上記第2の2(5)の前提事実において認定したとおり,原告は,別紙2の各「顧客名」欄記載のとおりの顧客に対して営業活動を行い,同「売上日」欄記載の日にちに通信機器等に係る契約を締結して,本件契約に基づく受託業務を遂行している。
(2) そして,証拠(甲6及び7)によれば,上記受託業務のうち平成26年6月30日を支払予定日とするものについては,その「販売契約額」を9万3000円と,「物品代金」を2万5280円と,「工事代金」を9000円とそれぞれ認めることができる(なお,被告作成の支払手数料計算書(甲6)の記載内容にかかわらず,ウィズネット作成の「工事結果一覧表」と題する書面(甲7)及び弁論の全趣旨によれば,実際に要した工事代金が9000円であることが明らかである。)から,上記1の争点①及び③に対する判断を前提として,上記第2の2(3)及び(4)の前提事実において認定した本件契約の定めを踏まえて当該受託業務に関して被告が支払うべき原告の報酬の額を算定すると,5万7075円となる(消費税相当額を含み,及び1円未満を切り捨てるものとする。)((93,000円-25,280円-9,000円)×90%×1.08=57,075.84円)ものと認めることができる。
したがって,被告は,原告に対し,5万7075円及びこれに対する支払予定日の翌日である平成26年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払義務があるというべきである。
(3) また,証拠(甲8)によれば,上記(1)の受託業務のうち平成26年8月10日を支払予定日とするものについては,同年6月開通分に係るネットワーク手数料であって,その「販売契約額」を8500円と認めることができる。そうすると,上記(2)と同様に,本件契約の定めを踏まえて当該受託業務に関して被告が支払うべき原告の報酬の額を算定すると,8262円となる(消費税相当額を含む。)(8,500円×90%×1.08=8,262)ものと認めることができる。
したがって,被告は,原告に対し,8262円及びこれに対する支払予定日の翌日である平成26年8月11日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払義務があるというべきである。
3 最後に,争点④(aクリニックへの納品不備による債務不履行に基づく被告の原告に対する損害賠償請求権の有無)について,判断する。
証拠(乙2,4,5及び509から511まで)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成22年頃,本件契約に基づく受託業務として,aクリニックからNX主装置L型を受注し,NX主装置1基につき72万5000円として,工事代金64万2300円,総額261万3600円とする平成22年7月22日付けの「御見積書」と題する書面を作成して,aクリニックに交付したこと(なお,NX主装置1基につき34万8000円とする同月26日付けで作成された形の被告名義の見積書(乙512及び513)が存在するが,当該見積書に基づいて被告がaクリニックから受注したものと認めることは,困難である。),それにもかかわらず,aクリニックからの受注がNX主装置M型であり,契約価格が総額262万5600円で,そのうち工事代金が23万2600円であるとの工事結果一覧表を被告に送付したため,被告がこれを前提としてNX主装置M型を発注し,工事業者をしてaクリニックに設置した上で,被告が原告に対して販売契約価格が262万5600円であることを前提に報酬計算を行うなどして報酬を支払ったことを認めることができる。そして,証拠(乙514)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,その後,aクリニックからの指摘を受け,平成26年1月頃,改めてNX主装置L型を設置する工事を行い,56万0552円相当の出捐をしたものと認めることができる。
このように,原告は,aクリニックからNX主装置L型を受注したにもかかわらず,NX主装置M型の受注を被告に告げるなどして,その受託業務の本旨に従った履行をしなかった結果,被告が56万0552円の出捐を余儀なくされたものということができる。
したがって,原告は,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償として,56万0552円及びこれに対する平成26年8月9日(上記第2の2(7)の前提事実において認定した催告の日の翌日)から支払済みまで民法(明治29年法律第89号)所定の年5%の割合による遅延損害金を支払う義務があるものというべきである。
4 上記2の争点②に対する判断において説示したとおり,原告は,被告に対し,未払報酬請求権として合計6万5337円並びにうち5万7075円に対する平成26年7月1日から,及びうち8262円に対する同年8月11日から各支払済みまで年6%の割合による遅延損害金請求権を有しており,他方で,上記3の争点④に対する判断において説示したとおり,被告は,原告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求権として56万0552円及びこれに対する同月9日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金請求権を有している。そうすると,本件相殺の意思表示により,これらが対当額において消滅することになるから,結局,現時においては,被告の原告に対する当該損害賠償請求権として49万5215円及びこれに対する同日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金請求権のみが存在するということになる(上記2及び3において説示したところから明らかなとおり,当該損害賠償請求権に係る上記3の催告時までには,当該各未払報酬請求権自体が発生していたものということができるから,当該催告の時をもって相殺適状にあったものと解するのが相当である。)。
第4 結論
以上によれば,原告の本訴に係る上記第1の1の各請求及び被告の反訴に係る請求のうち同2(1)の請求はいずれも理由がなく,被告の反訴に係る同(2)の請求は上記第3の4の限度において理由がある。
よって,原告の本訴に係る請求をいずれも棄却し,及び被告の反訴に係る請求を当該限度において認容するとともに,その余を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 江原健志 裁判官 水橋巖 裁判官 森智也)
〈以下省略〉
*******
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




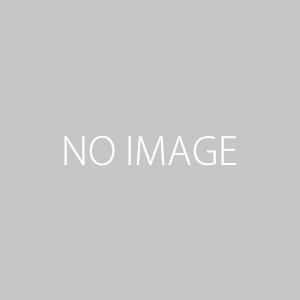
この記事へのコメントはありません。